今回はDAWの『Cubase』を選択するメリットについてご紹介したいと思います!
注意点も併せてお伝えいたしますので、購入を検討されている方の参考になればと思います。
Cubaseって何?

Steinberg社が開発した
DAWのこと
まず、Cubaseは”キューベース”、Steinbergは”スタインバーグ”と読みます。
ドイツのソフトウェア会社であるSteinbergがCubaseというDAWを開発しており、2005年よりヤマハさんの子会社となっています。
DAWにはCubase以外にもPro Tools(プロツールス / Avid Technology社開発)やStudio One(スタジオワン / PreSonus社開発)などいくつか存在し、総じて『DAW』と呼ばれています。
さて何度も『DAW』という言葉が出てきましたが、『DAW』と似たような『DTM』という言葉もよく使われますので簡単に説明いたします。
Digital Audio Workstationの略で”ダウ”と読みます。
作曲や編曲、ミキシング、マスタリング、レコーディングなどサウンドを制作する作業が可能なソフトウェアの総称。
※音楽制作ソフトとも言い換えて使うことが出来ますが、広義ではサウンド制作ソフトのことなんですね^^
使用例1:「この曲、何のDAW使って作ったん?」(訳:この曲はどの音楽制作ソフトを使って作ったのですか?)
使用例2:「この効果音って何のDAW使って作ったん?」(訳:この効果音は何というサウンド制作ソフトを使って作ったのですか?)
Desktop Musicの略で”ディーティーエム”と読みます。
パソコンを使って音楽を制作することを指します。
使用例:パソコンを買ったからDTMを始めてみようと思うねんけど、何かおすすめのDAWない?(訳:パソコンを買ったのでパソコンで音楽制作を始めてみようと思うのですが、何かおすすめの音楽制作ソフトは知りませんか?)
つまり、CubaseはDAWってことで、作曲、編曲、オーディオ編集、レコーディング、ミキシング、マスタリング、MAなどサウンド制作に関することは何でもできる素晴らしいソフトウェアなのです!
Cubaseにはグレードが5つ存在しており、それぞれ“Pro”、“Artist”、“Elements”、“AI”、“LE”という名前がついています。
Pro、Artist、Elementsは有償版。
AI、LEは無償版となっており、前者はYAMAHA製品やSteinberg製品に付属、後者は他社の製品に付属されているものとなります。
また、使用期限付きの体験版も公開されますので購入前に無償でお試ししたい方は是非ともSteinberg社のHPよりお試しください!
- CubaseはDAWである!
- DAWとは音楽制作ソフトのことであり、広義ではサウンド制作ソフトのこと
- Cubaseの最新バージョンは12(2022年3月現在)
- “Cubase Pro”、”Cubase Artist”、”Cubase Elements”の有償版が3種類ある
- “Cubase AI”、”Cubase LE”の製品付属の無償版が2種類ある
- 体験版もあるよ!
おすすめしたい3つの理由

Cubaseをおすすめしたい理由はたくさんあるのですが厳選して3つに絞りました。
DAWが欲しいと考えている方にとってとても大事な点だと思います。それらがわかったことで一歩を踏み出せる情報になっているかと思いますので参考にしていただければと思います。
- 日本語に対応している
- 買い切り製品である
- できることが豊富
1.日本語に対応している
ソフト自体の操作画面やマニュアル、それからサポートまで日本語に対応しています。
海外製品だと変な日本語に翻訳されていたりして日本語に変換されていてもわかりにくいなんてことがありますが、そういうったことが少ないです。
また、Cubaseの使い方やトラブル対応など、お役立ち情報も日本語でたくさん紹介されているので、GoogleやYouTube、X(旧Twitter)などで簡単に検索できて調べることができるのもとても助かりますよね。
日本国内ではCubaseユーザーが多いことが理由としてあるかと思います。
普段、日本語で生活している我々日本人とって、日本語に対応しているということはそれだけで安心感があります。
2.買い切り製品である
近年、たくさんのサブスクリプション(通称:サブスク)という定額サービスが増えてきていますが、Cubaseはサブスク対応していません(2024年10月現在)。
「欲しいけど使用頻度が少なくなってしまった時にも毎月代金を払い続けるのはちょっと…使わない月もあるかもだし…。でも、いつか使いたくなった時にまた契約するのも面倒だし…」
という方にとっては買いやすいのではないでしょうか?
サブスク製品にもメリットはありますが、買い切り製品は決断しやすいのかなと思います。
ちなみに、Cubase 11までは使用するためにドングルと呼ばれるUSB-eLicenser(ライセンス認証に必要なUSB接続のメモリースティックのようなキー)を別途購入する必要がありました。
こちらは、物理的にPCのUSBポートに差し込む必要があるためUSBポートを1つ占有してしまい、大きさは親指サイズくらいの小さいもので持ち運びの際など紛失しやすいというデメリットがありました。
ところが、Cubase 12からはライセンスの管理方式がアップデートされ、ドングルを使わずにCubaseを使用することが可能となりました。
3台のPCにアクティベートすることができ、わざわざ物理的にドングルをPCに刺すことなく使えるようになったことも、使い勝手の良さという点で昨今の時代に合った使い方ができるようになっています。
使用例:USBのポートを使用することなく、メインのデスクトップPC、サブのノートPC、その他の作業PCに入れるという使い方ができる
3.できることが豊富
Cubaseがあればサウンド制作の大部分が可能です!
サウンド制作においてできないことはないと思っていただいて問題ないかと思います。
以下に出来ることをざっと箇条書きいたしますので、自分がやりたいことと照らし合わせて想像してみてください。新しく挑戦してみたいことも出てくるかもしれませんね^^
- 音楽制作、作曲、編曲(音楽ジャンルは選びません。楽器やMIDIキーボードがなくてもOK)
- レコーディング、宅禄(※マイクなどの機材は必要です)
- ミキシング、マスタリング
- 効果音制作
- ボイス編集(歌やナレーションなど何でもOK※こちらもマイクなどの機材は必要です)
- MA、動画への音付け(動画編集される方にとっても役立つかと)
- 楽譜作成
- オンラインでセッションできる(SYNCROOMという無料のアプリが必要)
注意したいこと

サウンド制作において必要不可欠なソフトで大変便利なCubaseですが、注意したい点がいくつかあります。
- 最低限の機材が別途必要
- あれも欲しいこれも欲しいとなるかもしれない
- 良いサウンドが作れるとは限らない
1.最低限の機材が別途必要
悲しいかな、Cubaseを手に入れただけでは不十分なのです。
DAWを始めるうえでオーディオインターフェースとヘッドホンの2点は最低限必要になってきます。
PCと音のやり取りをするために必要な機材
“オーディオ I/O”などと言ったりします(オーディオ アイオー)
必要な理由
・音の遅延の解決
・やり取りする音の音質改善
PCに備わっているイヤホンジャックで作業することはNGです!
音のやり取りに遅延が発生してしまい作業するには厳しい状態となるからです。
“良い音で音を再生する”、“良い音で音を録音する”目的がありDAWには必要不可欠なアイテムとなっています。
※アコースティックギターやバイオリンなどの電子でない楽器、歌やナレーションなどの声の録音をしたい場合は別途マイクも必要になってきます。エレキギターやエレキベースなどはシールドと呼ばれるケーブルをオーディオインターフェースに差し込めば録音可能です。
おすすめのオーディオインターフェースはSteinbergの”UR12″という商品がお値段もお手頃で初心者にはちょうどいいかと思います。
≫Steinbergの”UR12″は以下よりどうぞ↓
PCと音のやり取りをするために必要な機材
必要な理由
・幅広いレンジの音域の聞き分け
フォン端子に変換すればイヤホンでも可能なのですが、イヤホンでは低音を聞き取ることが難しいです。
※みなさんがよく目にするイヤホンはステレオミニプラグやミニジャックなどと呼ばれる端子
※フォン端子はエレキギターなどでよく使われる、ステレオミニプラグよりも太い端子
みんながよく使うのがイヤホンなんだからいいじゃん、って思うかもしれませんが、それでもやはり低音の処理をするうえで最低限ヘッドホンはあった方がいいです。
イヤホンで楽曲のミックスをした後、ヘッドホンで聞いてみると「低音めっちゃ出てるやん!w」なんてことが起こってしまいますのでヘッドホンは定番のものでよいので用意することをおすすめします。
おすすめのヘッドホンはSONYの“MDR-M1ST”か“MDR-CD900ST”です。
MDR-M1STは低音域から高音域まで幅広くモニタリングすることが可能です!
MDR-CD900STはスタジオで定番商品です。MDR-M1STに比べると低音が少し弱い聞こえですがミックスからレコーディングまでしっかり対応可能です。
難点があるとするれば、長時間の作業に向いていないことです。ヘッドホンの内側の部分と耳があってしまい痛いんですよ…
長時間つけたい方は、開放型と言われる耳を覆うタイプのヘッドホンがありますのでそちらにしてみるのもいいかと思います!
2.あれも欲しいこれも欲しいとなるかもしれない
『音楽は課金ゲー』と言われるくらい、あれも欲しいこれも欲しいとなってくる可能性があります…!
その中でも代表的なもののひとつをご紹介します。それはプラグインというソフトシンセやエフェクト系の追加ソフトです。
ソフトシンセとは、名前からわかるようにシンセサイザイーを模したものやピアノやドラム、ギターの音色など楽器のライブラリのことを言います。
“音源”や”ソフト音源”などと言ったりしますが会話の中では”音源”と言う場合が多いように思います。
DAW付属のものでは音色に満足できない場合やさらなるクオリティアップ、足りない楽器や音色を追加したい場合に欲しくなってくると思います。中にはフレーズやパターンが収録されているものもあり作曲の時短にも貢献してくれます。
たくさんある中で初心者におすすめなのがNative Instrumentsからリリースされている、いくつかのプラグインがバンドルされているKOMPLET(コンプリート)シリーズです。いくつかグレードがありお高いものなのでまずは体験版からスタートしてみるといいかもしれません。事項で説明するエフェクト系のプラグインも含まれているので、プラグインとは何ぞや?を知るのにはいいきっかけかと思います。
プラグインは本当にたくさんの製品が各社からリリースされており、それぞれにいいところがあります。決して安い買い物ではないのでどれにすればいいか非常に悩みどころでしょう。
無償で公開しているプラグインもあり、プロのアーティストも使用しているものもたくさんあるので、調べて研究してみてください^^
3.良いサウンドが作れるとは限らない
音楽、効果音作りを始めようと思っている方に伝えたいことがあります。
それは『Cubaseがあるからといって良いサウンドが作れるとは限らない』ということ。
当然のことですが、様々なテクニックや道具を駆使して作り上げていくものなので、最初から誰でも目指したものが作れるとは限りません。地道ではありますが、コツコツと学んで成長していきましょう。
まとめ
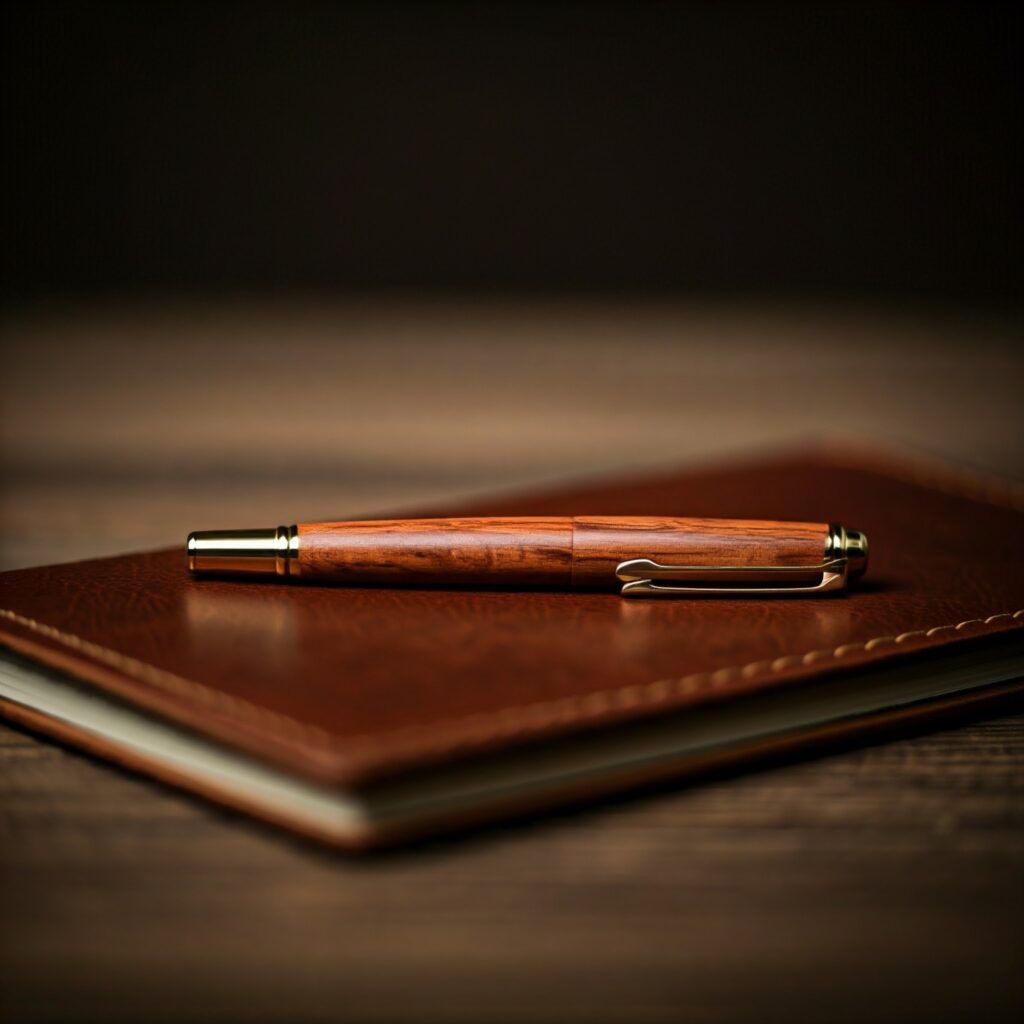
筆者は長年Cubaseを使用していることもあり使いやすくて他のDAWに目もくれませんが、初めて購入される方は安い買い物ではないので自分に合った製品を探すことは難しいかもしれません。
しかし、Cubaseは利用人口も多く、日本語の解説動画やマニュアルなども沢山ありますので困ったときに解決しやすいです。それでいてプロユースでもあるため、趣味からそのまま仕事として使っていくこともできてしまいます。
実際に触ってみたいという方は、楽器屋さんやオーディオショップなどお店に足を運んでみるのもいいかもしれません。お店によっては店頭で触らせてもらえるところもあるので、店員さんと話をしながら感触を確かめてみるのもいいでしょう。
ご自身のセンスを信じて、素敵なサウンドを作ってください!
Cubaseはそのための道具としてきっと活躍してくれることでしょう!
【番外編】プロの技を盗んで学ぼう!
自分が作曲した楽曲をプロにアレンジしてもらうというのも成長のきっかけの一つとしてもありかと思います。
『Super dolphin』というサービスでは、ご自身が作ったメロディや引き語り、編曲も進め打ち込みした楽曲をプロのクリエイターがアレンジ(編曲)し、プロクオリティの楽曲に仕上げてくれるというサービスです。
最終的には、すべての楽器トラックをまとめた2mixの音源の他に、パラデータ(全楽器トラックの単品ごとのオーディオデータ)やMIDIファイルなども納品してもらえるため、どういった楽器や音色を使って、どういったフレーズをどのタイミングで入れているのかなど編曲の勉強にもなるかと思います。
(プロのアレンジしたデータがのぞけるなんて、そうあることではありませんのでかなりお得かと!)
無料でオンライン相談が可能となっておりますのでプロの技をこの機会に盗んでみましょう!
\ 無料オンライン相談受付中 /
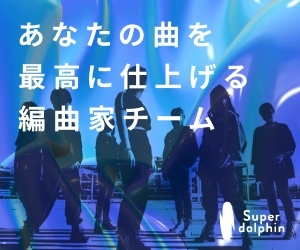

Cubaseの購入を検討されている方、気になっている方、これから始めてみようと思っている方々にとって少しでも参考になっていると嬉しいです。
以下の記事では、Cubaseと一緒に購入すべきものについて、音楽制作用途やレコーディング用途など目的別に必要なものをまとめておりますので是非チェックしてみてください。




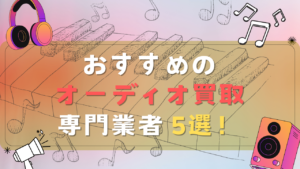
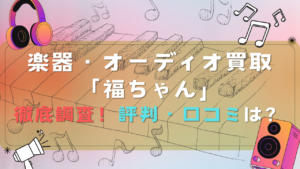

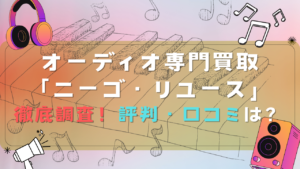
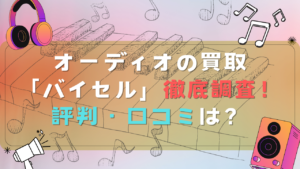
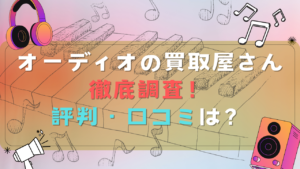
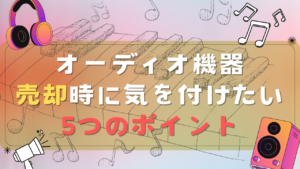
コメント